地元紙「十勝毎日新聞」にさざれいしの記事が掲載されました!
コロナ禍の中、子ども達の「学習の機会」をどのようにしたら提供できるかを考え、オンライン家庭教師を始めました。
勉強が苦手になっている子や不登校になっている子達にとって勉強は「あきらめる」しかないと感じている子も多いようです。
でも、「学び」は必ず人生を豊かにします。
必要としている子に、このオンライン家庭教師のサービスが届き、より良い「学習機会」を提供できるようにこれからも頑張ります!!🤗🤗

勉強が苦手な子や不登校の子を応援したい
コロナ禍の中、子ども達の「学習の機会」をどのようにしたら提供できるかを考え、オンライン家庭教師を始めました。
勉強が苦手になっている子や不登校になっている子達にとって勉強は「あきらめる」しかないと感じている子も多いようです。
でも、「学び」は必ず人生を豊かにします。
必要としている子に、このオンライン家庭教師のサービスが届き、より良い「学習機会」を提供できるようにこれからも頑張ります!!🤗🤗

「勉強はできなくてもいいけど、出来た方がいい」と考えている保護者は多いように思います。「勉強はむしろできない方が良いという」人は、よほど意地張ってますね😅😅😅
私がこれまで見てきた「勉強ができる子」はできる子というよりは「勉強が好きな子」と言った方があっている気がします。
私が出会ってきた「できる子」はこんな感じです。
まだまだありますが、大きく言うとこんな感じではないでしょうか。
よく、「あの子勉強できるよね。そっか、お父さんお医者さんだもんね。」というケースがあると思いますが、医者の子=勉強ができる は間違いです。
ここだけの話、優秀ではないお医者様の子を何人か見た事があります。💦
では、どうしたら勉強が得意になるのでしょうか?

まずは必要不可欠な要素として子どもが「勉強を好きであること」が挙げられます。
ここではっきり言っておきます!
勉強が嫌いな大人が子どもを勉強好きにさせることは100%できません!(ここから下は読む必要が無いと思います…💦)
ご自分が「勉強が嫌いです」という方は素直に「プロ」に任せた方がいいです。😅😅
自分が嫌いなものを子どもに好きになれと強制すると、逆に「信頼」を失い親子関係が悪化します。
「何で、お母さんが嫌いなものを俺に強制するのさ!」なんて言われちゃいますよ。
では勉強が好きになった子はどのようにしてそうなったのでしょう?
それは勉強が好きな人が身の回りにいた(いる)からです。
勉強を好きな人を見て「楽しそう!自分もやってみよう!」となるのです。
ここで必要になってくるのが「人が好き」という要素です。
子どもは「自分の好きな人」の興味を自分のものとしていきます。よく、「お姉ちゃんが中学で吹奏楽部だから、私も中学に入ったら吹奏楽やるんだ♬」なんて言っている子がいます。
この子はお姉ちゃんが好きなんです。
(スポーツ選手の子どもが「同じ競技」を選ぶことが多いのも同じ理屈で説明できると考えています。)
他にも友達が勉強好き、職場体験に言ったときにそこの人が熱心に教えてくれた、など勉強好きになるきっかけはさまざまです。
逆に「人が好き」となかなか思えない子の中にはこんな子がいます。
それは「親が人の悪口ばかり言っている」子。
もっとも身近な大人が「人を好きではない」事をたくさん感じた子は、なかなか人を信じること(好きになること)ができなくなります。
という事で子育て中の保護者のみなさん。悪口は子どもがいない所でいいましょう!😓
「子どもに好きになってもらえる人」が「勉強を教える」のが重要な要素の一つと言えます。
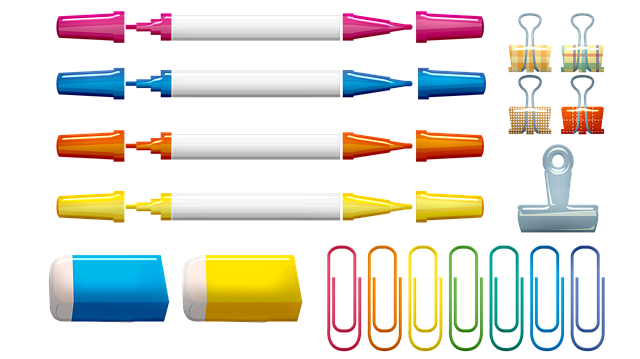
子どもが好きな大人になることが、子どもを勉強好きにさせる一番の近道です。ちなみに子どもが好きな大人の共通点を挙げるとこんな感じみたいです。
これらはほんの一部でまだまだあると思います。
9にある通り「大人自身が勉強を楽しんでいるか、どうか」は重要です。「プロ」は楽しんでいる様子をオーバーアクションで笑顔で表現し、子どもを惹きつけようとします。
これは「子どものご機嫌取りをして好かれたい」のではなく、「子どもを勉強好きにするための」必修事項なのです。
この土台を作ることができれば、大げさに言えば「授業を受けなくても」子どもが自ら学び、成績はぐんぐんあがります。
次回も引き続き「勉強が苦手な子」に教えるコツについてお伝えします!

ただいま「オンライン家庭教師さざれいし」の生徒を募集しています。無料体験授業もできますので、お気軽にお問合せください。案内にもあります通り、このサイトの申込みフォームからのお申込みで「入会金半額」となります。
勉強が苦手な子には「オンライン学習」が有効です。まずは説明を聞きたいという保護者の方もOKです!😀😀
訂正) 上記案内物の中学生コースの時間帯
誤 17:00~18:00 → 正 17:00~18:20
大変、申し訳ありません。さざれいしの生徒Tくんが教えてくれました。ありがとう。
大人になった時についていて欲しい能力。社会人が一番求められる能力ではないでしょうか。我が子にはぜひつけてあげたい能力ですよね。
では、どの様にして人間はその力を獲得していくのかを見ていきましょう。
実は人間は生まれた時には情報処理と応答のレベルは他の哺乳動物とあまり違いがないと言われています。そして成長するにしたがって複雑な情報に直面し、次第に頭を使う様になっていくのです。
この頃から「どうして」と「だって」の連発が始まり、人間の前頭連合野のはたらきは急速な発達をみせるのです。そして人間の幼児はそれまで並んでいたチンパンジーの知能を一挙に追い越すのだそう。
(生まれたばかりの赤ちゃんはチンパンジーと互角だって知ってました? 😅😅)
また、同時に人間として生きていくために、親を中心とした周囲の大人から「しつけ」を通じて様々なことを学習していきます。
ここで親は気合が入ってしまい一生懸命「しつけ」をしすぎる傾向がある気がします…。
答えを教えすぎてしまい、大人の思い通りにならなかったらとにかく「叱る」行為を繰り返していくと、子どもは考えることを辞めて「身の安全」を確保するために無条件に言うことを聞く事しかしなくなってしまいます。
これだけは避けたいですね。😫

子どもは一人遊びを経て子ども同士で遊ぶようになります。大人の配慮が無い状況で自由に遊べる事はこどもにとってとても大切な時間です。
ちょっと専門的な言葉でいうと「連合遊び」⇒「協同の遊び」への移行過程が特に大切です。
「連合遊び」は4~5歳児に見られる特徴がありますが、ポイントとなるのが自己中心的だということです。
平行遊びと違って互いが関係性を持つものの、あくまで自己中が目立つのがポイントです。
Aちゃん:「積み木遊びをしようよ!」
Bくん :「お団子作りがしたいな!」
Cちゃん:「セーラームーンごっこがしたい!」
お互い一緒に遊んでいるのは間違いありませんが、あくまで自分がしたい事を主張するのがポイントです。
ここで他の子の「感性」に初めて触れることになるのです。
「自分がこれをやりたいのに、何で他の子は一緒にやってくれないんだろう?」
子どもはこんなモヤモヤを感じながら試行錯誤していく事が重要なんです!!
そして「協同の遊び」は読んで字のごとく、みんなが協力しあうのが特徴です。
一緒にお団子作ったり、おままごとをしたりと、そういう特徴が見られます。また互いにルールを意識できるのもポイントで、ちょっとしたゲームを楽しむ事も可能です。
ここまでは、どっかのサイトで調べれば何かしら載っていると思います。
ここからは私の持論。
「子どものケンカを止めないで」
大人が子ども同士のいざこざをどこまで放っておけるかで「問題解決能力」を伸ばせるかが決まります。
大人が持っている解決方法は必ずしも子どもが直面している問題を解決できるとは限りません。
子どもにとっては貴重な「実践の場」。
残念ながら幼児教育においてこの貴重な「学びの場」は、大人から止めらてしまう事が多いようです。
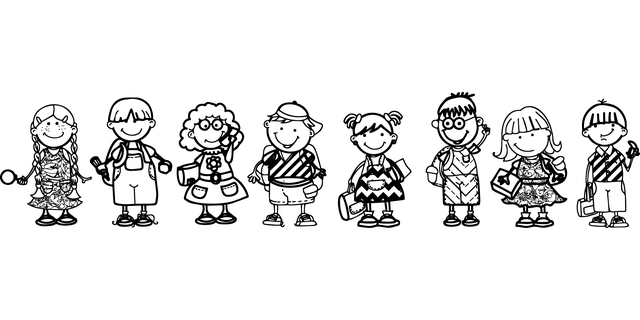
保育所等でよくある例。
Aちゃん「Bくん。おもちゃ、貸して。」
Bくん「いやだよ。今、使ってるんだから。」
大人「Bくん、貸してあげたら?ほら、
こっちのおもちゃで先生と遊ぼう。」
Bくん「えー嫌だよ。だってこれがいいんだもん。」
大人「みんなで仲良く順番で使おう。」
Bくん、怒っておもちゃを投げつけて壊す……。
また、こんな例もあります。
Aくん、Bちゃん、Cくんが3人で遊んでいます。
Aくんは鬼ごっこがしたかったらしく熱心に誘っています。でもBちゃん、Cくんはそんなに鬼ごっこには興味がなさそう。
結局、Aくんと他の2人は折り合いがつかず1人で遊ぶことになりました。
ここで大人が「3人で仲良く遊んだら?」と提案したらどうでしょう?
Aくんの「考える」機会はあるでしょうか?
何となくこうなって欲しいという大人の感情が最優先されると、子どもが自分の感情を確認する機会さえも失われてしまいます。
問題解決能力をつけるには、まずは問題を発見しなくてはなりません。
次に「発見した問題についてよく考える」ことが大切です。
そしてトライアンドエラーを繰り返して、自分なりの答えを見つけていくという作業がでてきます。
大人が介入せず、子ども同士で「遊ぶ」ことで問題解決能力はどんどん伸びていきます。
・子供のケンカを止めないで!
・子ども同士で自由に遊ばせると問題解決能力の基礎ができる!
