子どもの話をよく聞くこと
当たり前の事にしか聞こえないと思われますが、少し詳しくお話ししたいと思います。
「子どもと向き合いながらじっくり教えます!」と言われると「どっかの塾のキャッチコピーみたいだな。」と思われる方もいますよね。
言葉にするのは簡単ですが実際はそんなに簡単ではありません💦
今日は向き合う際の基本的姿勢(心理・言葉・外見)やスキルについてお伝えしていきたいと考えています。
まずは心理面の理解から。😄
勉強が苦手な子(不登校の子)は自信を無くしている子がほとんどです。
できていなくてもできている風を装いたくなったりします。
また、できていないことを「隠したい」という気持ちを少なからず持っているものです。
その時に子どもの言葉だけを鵜呑みにしてしまうと、子どもの不安な気持ちに気づけず「学びたい」という気持ちを起こさせてあげることができません。
子どもにとっては、大好きな人だから「弱い部分を見せたくない。」という気持ちも強く働きます。
「ここが分からない。」と告白することは子どもにとってとても勇気がいることなのです。
「〇〇くん、分かった?」「うん。分かった。」のやり取り最中の声のトーン、表情を確認しながら子どもにアウトプットしてもらい理解度を確認していきます。
そして、子どものアウトプットを引き出すのに必要なのが、いわゆる「傾聴」というやつです。
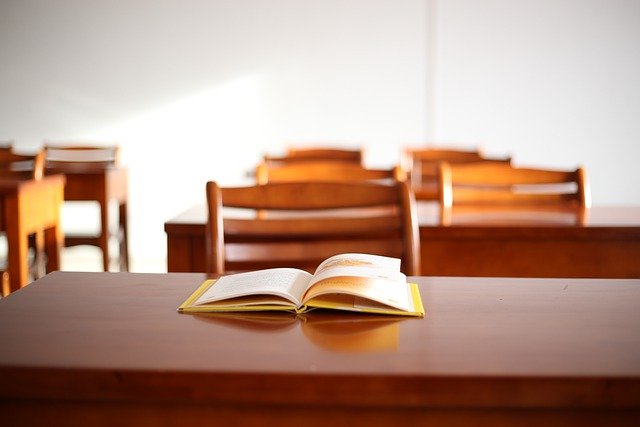
次に「教える側の」基本的姿勢についてです。😄
福祉の業界ではもはや常識的な言葉ですが、教育業界ではまだまだ一般的ではないかもしれませんので簡単にご紹介。
<傾聴とは>ロジャースの3原則
1.共感的理解 (empathy, empathic understanding)
相手の話を、相手の立場に立って、相手の気持ちに共感しながら理解しようとする。
2.無条件の肯定的関心 (unconditional positive regard)
相手の話を善悪の評価、好き嫌いの評価を入れずに聴く。相手の話を否定せず、なぜそのように考えるようになったのか、その背景に肯定的な関心を持って聴く。其のことによって、話し手は安心して話ができる。
3.自己一致 (congruence)
聴き手が相手に対しても、自分に対しても真摯な態度で、話が分かりにくい時は分かりにくいことを伝え、真意を確認する。分からないことをそのままにしておくことは、自己一致に反する。
このように傾聴とは「聞き手側の姿勢」の事をさしますが、実はこれによって相手のアウトプットが引き出される事が大切なポイントとなります。
前述したような基本姿勢(心理)で子どもの話を聞きます。
また、実際に話を聞く際には次の事を気をつけると良いでしょう。
- 相手の目を見て話す(表情豊かに明るく朗らかに)
- 相手の言葉を繰り返す(自分の言葉を繰り返している→承認された!)
- 相手の言葉に質問する(自分のことを深く理解しようとしてくれている!)
そして、傾聴しながら子どもから聞き出した「わからない部分」を分析していくのです。

分からない事をどこまで分割できるかが勝負
最後にスキル面からお話しします。😄
高学歴の人が必ずしも良い先生になれるわけではありません。それは多くの人が自分が理解してきた過程で他人にものを教えようとするからです。
高学歴の人はその優秀さゆえに「理解のステップ」を自身が一足飛びに駆け上がっていることが多く、その途中で理解できなくなるという経験をしていないのです。
(もちろん高学歴の方でも相手の状況をよく想定できていて、細かいステップを見つけてあげられる人もいらっしゃいますよ。)
では、例を挙げてみたいと思います。
「異分母どうしの足し算」は「通分」してから計算してね!
↓
生徒が固まる・・・(何も言わず厳しい表情🙄)この時は例えばこんな事が考えられます。
・通分ってどうやるの?🤔
・最小公倍数ってなに?🤔
・その時、分子はどうするの?🤔
・掛け算・割り算の時はどうなの?🤔
・そもそも何で通分する必要があるの?🤔
※場合によっては掛け算の九九が不安定なことだってあります。
分からない所は本当に人それぞれです。決めつけてパターン化してしまうと、その子に合わないステップにしてしまい、目の前にいる子の学びたい気持ちを折ってしまいかねません。
福祉では相手の漠然とした不安を解消していく際に「傾聴」を使いながら、相手にアウトプットしてもらい「解きほぐして」いきます。
その感覚と「勉強が苦手な子」に教える行為は非常に近いと思います。
その子が話しやすい環境をどのように作り、どれだけ細かくステップを設定できるかが「分かった!」の笑顔をつくる大切なポイントと言えそうです。

