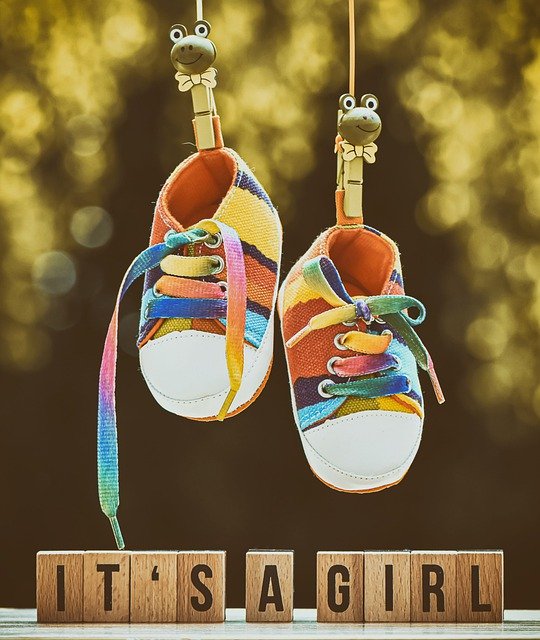問題解決能力をつける
大人になった時についていて欲しい能力。社会人が一番求められる能力ではないでしょうか。我が子にはぜひつけてあげたい能力ですよね。
では、どの様にして人間はその力を獲得していくのかを見ていきましょう。
実は人間は生まれた時には情報処理と応答のレベルは他の哺乳動物とあまり違いがないと言われています。そして成長するにしたがって複雑な情報に直面し、次第に頭を使う様になっていくのです。
この頃から「どうして」と「だって」の連発が始まり、人間の前頭連合野のはたらきは急速な発達をみせるのです。そして人間の幼児はそれまで並んでいたチンパンジーの知能を一挙に追い越すのだそう。
(生まれたばかりの赤ちゃんはチンパンジーと互角だって知ってました? 😅😅)
また、同時に人間として生きていくために、親を中心とした周囲の大人から「しつけ」を通じて様々なことを学習していきます。
ここで親は気合が入ってしまい一生懸命「しつけ」をしすぎる傾向がある気がします…。
答えを教えすぎてしまい、大人の思い通りにならなかったらとにかく「叱る」行為を繰り返していくと、子どもは考えることを辞めて「身の安全」を確保するために無条件に言うことを聞く事しかしなくなってしまいます。
これだけは避けたいですね。😫

子ども同士で遊ぶ
子どもは一人遊びを経て子ども同士で遊ぶようになります。大人の配慮が無い状況で自由に遊べる事はこどもにとってとても大切な時間です。
ちょっと専門的な言葉でいうと「連合遊び」⇒「協同の遊び」への移行過程が特に大切です。
「連合遊び」は4~5歳児に見られる特徴がありますが、ポイントとなるのが自己中心的だということです。
平行遊びと違って互いが関係性を持つものの、あくまで自己中が目立つのがポイントです。
Aちゃん:「積み木遊びをしようよ!」
Bくん :「お団子作りがしたいな!」
Cちゃん:「セーラームーンごっこがしたい!」
お互い一緒に遊んでいるのは間違いありませんが、あくまで自分がしたい事を主張するのがポイントです。
ここで他の子の「感性」に初めて触れることになるのです。
「自分がこれをやりたいのに、何で他の子は一緒にやってくれないんだろう?」
子どもはこんなモヤモヤを感じながら試行錯誤していく事が重要なんです!!
そして「協同の遊び」は読んで字のごとく、みんなが協力しあうのが特徴です。
一緒にお団子作ったり、おままごとをしたりと、そういう特徴が見られます。また互いにルールを意識できるのもポイントで、ちょっとしたゲームを楽しむ事も可能です。
ここまでは、どっかのサイトで調べれば何かしら載っていると思います。
ここからは私の持論。
「子どものケンカを止めないで」
大人が子ども同士のいざこざをどこまで放っておけるかで「問題解決能力」を伸ばせるかが決まります。
大人が持っている解決方法は必ずしも子どもが直面している問題を解決できるとは限りません。
子どもにとっては貴重な「実践の場」。
残念ながら幼児教育においてこの貴重な「学びの場」は、大人から止めらてしまう事が多いようです。
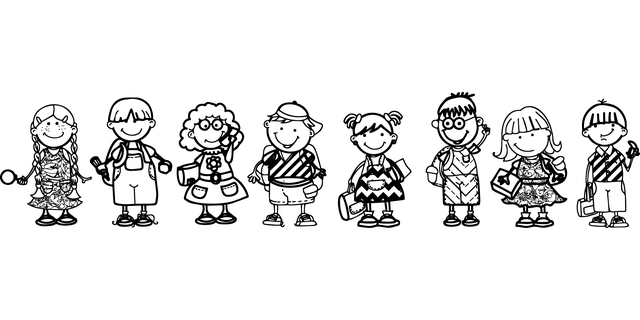
子ども同士で遊ぶと…
保育所等でよくある例。
Aちゃん「Bくん。おもちゃ、貸して。」
Bくん「いやだよ。今、使ってるんだから。」
大人「Bくん、貸してあげたら?ほら、
こっちのおもちゃで先生と遊ぼう。」
Bくん「えー嫌だよ。だってこれがいいんだもん。」
大人「みんなで仲良く順番で使おう。」
Bくん、怒っておもちゃを投げつけて壊す……。
また、こんな例もあります。
Aくん、Bちゃん、Cくんが3人で遊んでいます。
Aくんは鬼ごっこがしたかったらしく熱心に誘っています。でもBちゃん、Cくんはそんなに鬼ごっこには興味がなさそう。
結局、Aくんと他の2人は折り合いがつかず1人で遊ぶことになりました。
ここで大人が「3人で仲良く遊んだら?」と提案したらどうでしょう?
Aくんの「考える」機会はあるでしょうか?
何となくこうなって欲しいという大人の感情が最優先されると、子どもが自分の感情を確認する機会さえも失われてしまいます。
問題解決能力をつけるには、まずは問題を発見しなくてはなりません。
次に「発見した問題についてよく考える」ことが大切です。
そしてトライアンドエラーを繰り返して、自分なりの答えを見つけていくという作業がでてきます。
大人が介入せず、子ども同士で「遊ぶ」ことで問題解決能力はどんどん伸びていきます。
まとめ
・子供のケンカを止めないで!
・子ども同士で自由に遊ばせると問題解決能力の基礎ができる!